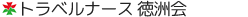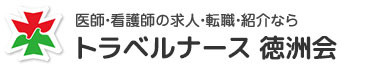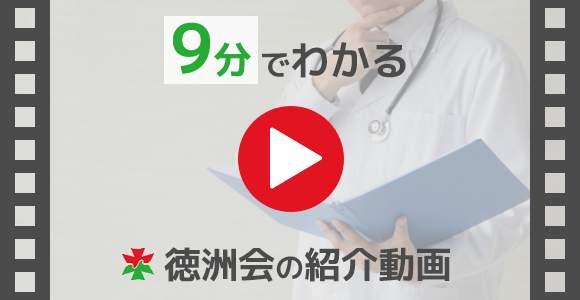徳洲新聞2025年(令和7年)8/4月曜日 NO.1503より
詳細は「徳洲新聞ニュースダイジェスト」をご覧ください。
第9回徳洲会グループQI大会を開催し、各カテゴリの優秀演題の発表と表彰式を行った。応募演題数は過去最多だった前回と同数の132演題。QI大会は、個々の病院・施設の取り組みからベストプラクティス(最良の実践)を吸い上げ、知見を共有して水平展開を図り、グループ全体の医療の質向上や業務改善の推進につなげる重要な取り組みだ。

東上理事長(右から4人目)を囲んで優秀演題賞受賞者らが記念撮影
QI大会は6つのカテゴリに分けて演題を募集。一定の評価基準に沿って厳選した各カテゴリ3演題・計18演題を対象に、eラーニングの仕組みを活用してグループ全職員の投票により、優秀演題を選出。総投票数は8万6,161票に上った。セミナー会場では、各カテゴリでトップ投票の優秀演題6題に加え、理事長推薦演題を合わせた計7演題の発表を行った。
一般社団法人徳洲会(社徳)の深野明美・医療安全・感染管理部部長が司会を務め、成田富里徳洲会病院(千葉県)の三浦千賀子・看護部長、湘南鎌倉総合病院(神奈川県)の芦原教之・事務部長、羽生総合病院(埼玉県)の髙橋暁行院長が順に座長を担った。発表順に演題を紹介する。
はじめに、「臨床」のカテゴリで選出された湘南鎌倉病院の今井尚美・心臓血管外科診療看護師が、「心臓血管外科急変時初期対応までの時間短縮への取り組み」をテーマに発表。開胸術後の心停止は特殊な急変対応で、知識・経験不足による対応の遅れが懸念されたため、心停止対応プロトコルの学習会や蘇生対応のシミュレーション訓練を実施。初期対応までの時間を計測し、訓練実施前後で比較した結果、時間短縮につながった。
続いて「職員目線・働き方改革」のカテゴリでは、羽生病院の浜島一代・外来・救急看護師長が「タスクシフト・タスクシェアによる多職種との業務協働」と題し発表。
2021年の法制度改正により、検査のための静脈路確保が診療放射線技師と臨床検査技師に認められた。研修や指導を受けたうえで両職種による静脈路確保を開始し、外来看護師の業務負担軽減などにつなげることができた。
「医療安全」では、「患者さまの病気を見落とさないために」という演題が選出された。発表は、白根徳洲会病院(山梨県)の鶴田文・医師事務作業補助者副主任。放射線画像読影医から異常所見指摘があった患者さんについて、患者さん本人や家族に医師が適切に説明を行うよう促す取り組みなどを行った結果、説明漏れを0%にすることができた。
「患者目線」は湘南藤沢徳洲会病院(神奈川県)の東靖広QIセンター課長が発表した「外来予約におけるオンライン化の効果と課題」が選出。同院患者総合支援センターは予約センターと病診連携室を兼ね、業務が煩雑となっており、電話を受けきれないことが課題だった。外来予約のオンライン化を導入し、対応件数の増加やクレームの低減につながった。
理事長推薦演題は、宇治徳洲会病院(京都府)の前川真帆・歯科衛生士主任が発表した「周術期口腔機能管理の対象拡大による経営的な影響」が選ばれた。同院はICU(集中治療室)や脳卒中ケアユニットでの歯科衛生士による専門的口腔ケアの積極的な介入を開始。口腔内の潰瘍や動揺歯などへの早期対応が可能となり、患者さんの利益につながると同時に、増益にも寄与した。
「地域社会」では近江草津徳洲会病院(滋賀県)の飯田有紀・理学療法士主任が発表した「地域住民の健康増進に向けたフレイル予防教室の取り組み」が選出された。
フレイル(虚弱)予防の健康教室を定期的に開催、リピーター率50%を目標に掲げ、継続的に参加してもらうことを目指した。筋力測定や講演、運動などを内容とし、認知度向上などに努めた結果、リピーター率53%を達成した。
「経営」は吹田徳洲会病院(大阪府)の石田朋子・臨床検査技師主任が発表した「廃棄製剤削減への取り組み~吹田徳洲会病院の軌跡~」が選出。
血液製剤の廃棄削減を目指し、電子カルテ上の連絡ツールの活用や、手術待機血に対する翌日確認、ミニ医局会を利用した医師への連絡など改善策を実施。廃棄率は年々減少し、24年10月末時点で0.18%と、全国的に推奨されている0.5%未満をクリアした。
発表終了後、東上震一理事長は「QI大会は良い演題を選出し、グループ内に広く展開することを目的としています。今回どの演題も、すぐにでも各病院が取り入れ、実践するのにふさわしい良い演題ばかりでした」と総括した。
- 第29回日本気胸・嚢胞性肺疾患学会 「新たなC.Q.への挑戦」がテーマ 福岡大学病院福大メディカルホールで9月5日から
- 問いを立てる力を医療者へ 原点に立ち返る学術集会に ――大渕副院長に聞く
- 7月度 徳洲会グループ 医療経営戦略セミ 税引き前利益が計画達成 非常勤医師など人件費適正を
- 徳洲会国際心臓血管セミナー 神奈川・葉山で9月13日から
- 目指せ!ナイチンゲール 第51回
徳洲新聞2025年(令和7年)8/4月曜日 NO.1503より
詳細は「徳洲新聞ニュースダイジェスト」をご覧ください。